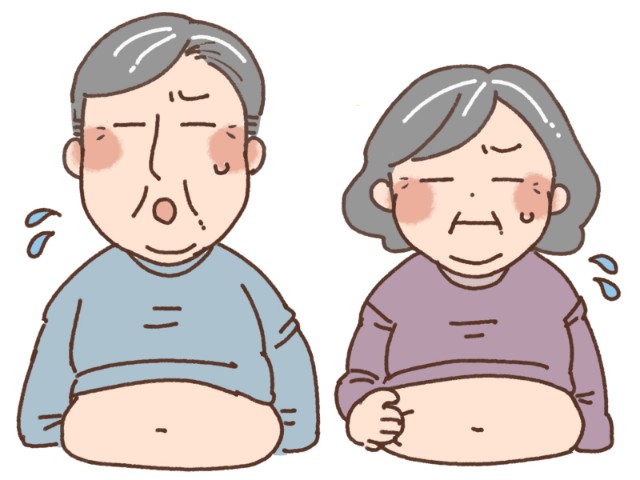「太っているのは、本人の努力が足りないから」「意志が弱いからだ」
あなたは、肥満に対して、まだそんな古い考えを持っていませんか?
もしそうなら、その認識は今日でアップデートが必要です。
最新の医学は、「肥満症」を、単なる生活習慣の乱れの結果ではなく、遺伝的要因や社会環境が複雑に絡み合い、命にかかわる合併症を引き起こす深刻な「慢性疾患」として位置づけています。
本記事では、「自己責任論」の壁を打ち破り、なぜ肥満症が治療すべき病気なのか、そして最新の治療法まで、具体的な情報とエビデンスに基づいて、わかりやすく解説します。
1.「肥満」と「肥満症」は全く違う!〜病気としての定義〜
まず大前提として、「肥満」と「肥満症」は明確に区別されます。
肥満 (Obesity)
BMI(体格指数)が25以上の状態。これは「体重の増加」という状態を指すに過ぎません。
肥満症 (Obesity disease)
肥満が原因で、一つ以上の健康障害を合併している状態、または内臓脂肪型肥満と診断され、医学的な治療が必要な状態です。
日本肥満学会では、以下のような合併症が一つでもあると、「肥満症」と診断されます。
- 糖尿病、耐糖能障害
- 高血圧症
- 脂質異常症
- 高尿酸血症(痛風)
- 脂肪肝(NAFLD/NASH)
- 睡眠時無呼吸症候群 (SAS)
- 月経異常、不妊症
- 変形性関節症、腰痛 など
つまり、「肥満症」は、他の病気を引き起こす原因となる病気であり、放置すれば健康寿命を縮め、QOL(生活の質)を大きく低下させるのです。
2.「自己責任論」が治療を妨げる深刻な壁
なぜ、これほど重い病気が「自己責任」として片付けられてしまうのでしょうか?
その根底には「オベシティ・スティグマ(肥満への偏見)」という問題があります。
オベシティ・スティグマの害悪
社会には「食べ過ぎ・運動不足」という単純なイメージが強く、肥満症の人に対して「怠惰」「意志が弱い」といったネガティブなレッテルを貼りがちです。
日本肥満学会も、このスティグマが、肥満症を持つ人々が適切な医療にアクセスするのを妨げていると警鐘を鳴らしています。
偏見を感じることで、
受診をためらう
「また生活指導を受けるだけ」「どうせ自分のせいだと言われる」と感じ、医療機関から足が遠のく。
精神的負担
抑うつや自尊心の低下につながり、かえって過食や引きこもりを招く悪循環に陥る。
社会的不利益
就職、昇進、人間関係など、社会生活のあらゆる場面で不当な扱いを受ける。
肥満は多因子が絡む「慢性疾患」
最新の研究では、肥満症が個人の意志だけでは解決できない複雑なメカニズムを持つことが明らかになっています。
遺伝的要因
肥満になりやすい体質、脂肪細胞の大きさや数、食欲を司るホルモン(レプチンなど)の感受性は、遺伝で決まる部分が大きいことがわかっています。
食環境・社会環境
安価で高カロリーな加工食品の普及、運動をしない生活を強いられる都市環境、仕事のストレスなど、
個人ではコントロールしにくい社会的要因が、誰もが肥満になりやすい「肥満原生環境」を作り出しています。
3.命を脅かす!肥満症が引き起こす重篤な合併症
肥満症の深刻さが「自己責任では済まされない」と言われる最大の理由は、
その合併症が直接的に死因の上位を占める病気につながるからです。
致命的な心血管疾患リスク
肥満症は、高血圧、脂質異常、糖尿病という「死の四重奏」を構成し、動脈硬化を急速に進行させます。
その結果、
- 心筋梗塞: 心臓の血管が詰まる。
- 脳梗塞: 脳の血管が詰まる。
といった、命にかかわり、かつ重い後遺症を残す病気を引き起こすリスクが格段に高まります。
睡眠時無呼吸症候群 (SAS)
首周りの脂肪沈着により、睡眠中に何度も呼吸が止まる病気です。
日中の眠気だけでなく、突然死のリスクや、高血圧・心臓病の悪化に直結します。
がんとの関連
肥満は、大腸がん、乳がん(閉経後)、子宮体がん、肝臓がん、腎臓がんなど、複数のがんのリスクを高めることが明らかになっています。
脂肪組織から分泌される炎症性物質やホルモンが、がんの発生や進行に関与するとされています。
最新のエビデンスでは、肥満者の約40%が5年以内に他の慢性疾患を発症するというデータもあり、早期の介入がいかに重要であるかを物語っています。
4.治療のパラダイムシフト〜最新の薬物療法と医療介入〜
「食事と運動で痩せる」のが基本ですが、それだけでは不十分なケースが多いからこそ、肥満症治療は近年、大きな転換期を迎えています。
新しい「抗肥満薬」の登場
食事・運動療法で効果が得られない重度の肥満症患者に対し、画期的な効果を示す新しいタイプのGLP-1受容体作動薬などの治療薬が注目されています。
これらの薬は、脳の食欲中枢に働きかけて食欲を抑えたり、血糖値をコントロールしたりする作用を持ちます。
単なる減量だけでなく、心血管疾患や慢性腎臓病の抑制といった重篤な合併症リスクを減らすエビデンスも得られつつあります。
【重要ポイント】
「3%程度の減量でも合併症の改善が認められる」一方で、
「重度の合併症の改善にはしばしば10〜20%程度の減量が必要」とされており、
この大きな減量目標を達成するために、薬物療法や外科的治療が重要な選択肢となりつつあります。
肥満外科手術
極めて高度な肥満症(BMIが35以上など)で、薬物療法でも効果がない場合、
胃の一部を切除・縫合する肥満外科手術(減量・代謝改善手術)が検討されます。
これは、減量効果が最も大きく、糖尿病などの合併症を劇的に改善させる力を持っています。
まとめ:必要なのは「努力」ではなく「治療」と「社会の理解」
肥満症は、「単なる努力不足」ではなく、治療を必要とする深刻な慢性疾患です。
あなたが今日からできることは、以下の二つです。
偏見を捨てる
肥満症は本人のせいではないことを理解し、周囲の人への無理解な言動をやめること。
適切な医療に繋がる
もし自分や家族が肥満症かもしれないと感じたら、「肥満症専門医」や内科などの医療機関をためらわずに受診すること。
肥満症の治療目標は、「体重を減らすこと」だけでなく、「合併症を改善・予防し、健康寿命を延ばすこと」です。
この新しい認識が広がることで、多くの命が救われ、より質の高い人生を送れる社会へと変わっていくでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。